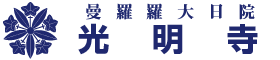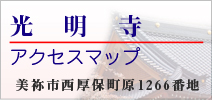我が山寺のホームページは、私が言うのもなんですがよく出来ていると思います。と、いうのもホームページ上での見せ方が上手いので、光明寺が現実より随分良い寺に(いろんな意味で)見えるのです。この手のことに詳しい人が見ればすぐ解ると思いますが、個人が趣味の延長でちょこちょこっと作成したサイトではありません。あちらこちらに高度な技術が駆使されています。トップ画面の動画などは実に見事なものです。私にそんなマネが出来るはずもなく、優秀なプロが気合いを入れて構築して下さったすこぶるまっとうなサイトです。ここまでやると結構なお金がかかります。いや正確にはかかるはずですと申し上げます。実際、山寺にそんなお金が負担出来るはずもなく、我が光明寺のサイトを立ち上げるプロジェクトに賛同し協力して下さった関係者の尽力の賜です。お坊さんらしい言葉で(坊さんでなくてもよく使うのだけど...)表現すると、まさに「みなさんのおかげで」と言うべき典型的なケースです。
さてタイトルに掲げた「おかげさま」に絡めて、今回は私の最初の本格的な坊主修行について書きます。43才になる直前、親や周囲の反対を押し切りサラリーマン生活から一転仏門に入ることにした私は、ある意味大変おばかなチャレンジャーでした。お坊さんになるということがどういうことなのかをよく理解しないで、この世界へ飛び込んだのです。実際わが宗派の僧侶になる道程は、私の想像をはるかに上回る厳しいものでした。「後悔しなかった」と言えば嘘になります。私の家は代々真宗本願寺派の門徒です。そして私は長男です。私もいわば真宗門徒の一人(本人にその自覚は大してなかったのですが)だったのです。ですから浄土真宗のことなら多少は知っていました。おばあちゃんの法事などで実家の菩提寺の住職にお会いし、親しくお話しする機会もありましたし、サラリーマン時代には、社員やその家族に不幸があった際に会社関係者の一人として毎度々葬儀に出席しておりましたので、葬儀のお経(浄土真宗)は随分聴かせて頂いておりました。私が住む旧美祢市は真宗本願寺派の勢力が非常に強固な土地です。お寺と言えば本願寺派で他宗派の寺院はごく少数(実質的に3ケ寺)です。私が首を突っ込むことになった妻の実家は同じ「南無阿弥陀仏」の宗派ではありましたが、圧倒的な真宗ではなく幸か不幸か浄土宗の西山派です。それでも似たようなもんだろうとたかをくくっていたら、とんでもないことになりました。
まず驚いたのはお経が全くといって良いくらい違うのです。しかも坊さんになるには、雪がちらつく3月にふんどし姿で水をかぶる行(水行)をしないといけないのです。それも一日三回です。実際、朝の水行は悲惨でした。まだ真っ暗な中、底冷えのする行場で氷が張ろうかという冷水をバサバサかぶり、それから夜明け前のおつとめに挑むのです。しかし本当のお楽しみ?(苦行)は水行ではありません。水行に続くおつとめこそが鬼門でした。おつとめは、まず御影堂(本山における本堂)の堅い畳の上で裸足のまま長時間の正座を強いられます。その後広い境内の諸堂を巡回して、それぞれの場所でも読経を行います。おつとめが終わると食堂(仏教ではじきどうと読む)での食事になりますが、板張りの上に薄っぺらなゴザが敷いてあるだけの場所で食事をとります。当然食事中も正座です。結局これら一連の正座が一番つらかったのです。
私はもともと正座は苦手というか出来なかったのです。学生の時にくるぶしの関節を骨折したこともあり、足首が伸びなくて正しい正座の姿勢がとれません。この状態で朝昼夕のおつとめをこなし最後は食堂でのだめ押しです。それはハッキリ言って拷問でした。(関係者のみなさま、正直なことを書いて申し訳ありません)ですから痛みをまぎらわすため、おつとめはお経に集中するしかありません。いきおい読経の声は大きくなります。腹の底から絞り出すような、なんとも悲惨なお経です。三日もするとのどはつぶれてほとんど声が出ない状態になります。それでもヒィーヒィーいいながらお経を読まなければなりません。行に参加している他の仲間も似たようなものです。ほとんどはお寺の子として生まれ、この行に参加している若者たちです。この行(加行:けぎょうと呼ぶ)の最中に44才となる私とは、親子ほど年の離れている子も沢山います。寺に生まれたといっても、いずれも今時の若者ですから私と大して変わりません。やはり正座が一番の苦痛です。痛みに耐えて無理するあまり読経中に失神して倒れる者、ひきつけを起こしたような状態になり病院送りになる者など実に恐ろしい光景です。私も失神しかけて、目の前の経机にしこたま頭を打ちつけた事があります。
さて、ここまで厳しいと挫折者が出て当然です。そして一度あきらめると「再び挑戦することは出来ないものだ」と聞きました。まったくその通りであろうと思います。しかし彼らは宿命を背負ってこの行に参加しているのであり、そうそうギブアップするわけにも行きません。だからこそ、そこまで耐えられるのかもしれません。この強烈な修行(加行)を指導されている関係者の気苦労も相当なものです。なぜなら、行に参加している若者たちはいわば我が宗門の次代をになう人材です。その大切な若者達を預かり、彼らの師匠(現在ではたいてい父親ですね)になり変わってきっちり指導し、我が宗門の僧侶として恥ずかしくないように仕上げ、かつ無事に生還させなければなりません。加減を誤り彼らをここでつぶしてしまえば、それは末寺の将来を閉ざすことであり、我が宗門の将来を左右することにもなりかねません。かといって甘いことを言っていては本物の修行にはなりません。こういう微妙な苦行難行を我々は「生かさず殺さずの行」と呼んだりします。(ウソですよー、でも臆病な私は、これは命がけだ...と本気で思ったのは事実です)そのあたりのさじ加減は実に微妙であり責任重大です。指導して下さる僧侶は、いずれも自分の寺のことは放り投げて次代をになう人材育成のために長期間本山にこもっているのです。
この世界に入って解ったことですが、本山を頂点とする宗派組織というものは、ちょうど花道や茶道などの家元制度とよく似たシステムです。(ただし家元制度や浄土真宗が世襲であるのに対して、我が宗派も含め多くの本山では、所属する末寺から頂点の僧侶が選挙等で選ばれますし、末寺の後継者も世襲前提ではありません)宗派に所属するお坊さんは、本山よりお墨付き(僧侶のお免状)を頂かないとその宗派の僧侶にはなれません。そのお免状を頂くために我が西山浄土宗で課せられている、いわば通過儀礼がこの加行です。そして自分の寺の住職に就任するには、さらに総本山光明寺より住職のお免状を頂かないといけません。そういう意味では本山の威光というものは絶大です。しかし宗派組織というものは、いわば本山を事務局とした一種の組合みたいなものでもあります。そこに所属する各末寺はいずれも一宗教法人として本来独立した存在です。末寺の住職とは各末寺の代表者(登記上では代表役員)でありいわば社長です。いくら組織や本山のためだと言っても、自分のところがダメになったら話にならんわけです。ですから本山で後進の指導をするということは、そうそう引き受けられることではありません。自分の寺のことは大なり小なり犠牲にすることになるのです。ここで引き合いに出すのは安易かもしれませんが、私お得意の言葉「菩薩道」を実践できる人であり、またいろんな意味で一流の僧侶でなければ務まらないことです。自分の寺はみんな大事です。しかし我が宗門の発展のために、さらには世のため人の為の思いが無いと出来ることではありません。
私は毎年この加行が行われている時期に本山へ行きます。ほんのささやかな差し入れをするためと、苦痛に耐えてそれでもお坊さんになろうとしている若い人たちを励ましたいからです。そして一緒に苦しい加行を耐え抜いた仲間たちと再会し、それぞれの近況を報告しあうためです。彼らとは親子ほど歳がはなれていますが、いわば同級生です。加行が終了する満行の前日(いわば卒業式の前日です)に、監督責任者の櫻井師よりそれぞれ総括の感想を述べよと指示がありました。その時私が述べさせて頂いた言葉を今もよく覚えています。「明日私は正式に僧侶になります。これもご指導下さった監督のみなさん関係者のみなさんのおかげです。そして同行の(苦楽を共にした修行仲間)みなさんのおかげです。これまでこんなに感謝の気持ちに溢れたことはありません。仏門に生きることになる者として、いわば明日が始まりの日だと思っています。お坊さんになっても修行は一生続きます。終わりはありません。そして同行のみなさん(みなさんは若いので)たぶん私のほうが一足先に阿弥陀さんのところへ行くと思いますが、待っていますからまたこのオッチャン(修行仲間の彼らから私はそう呼ばれていた)と一緒に修行して下さい。私たちは永遠に同級生なのですから」などと発言したものです。思えば加行中のあの時こそが、私の人生において一番純粋でまじめな良き人であったのかもしれません。それくらい真摯な気持ちで取り組まなければ無事に満行を迎えることは出来なかったのです。しかし月日は流れ今ではすっかり煩悩にまみれた私でございます。「ああ、阿弥陀様お許し下さい」
おかげさま(お陰様)とは「あなたのお力添えで」ということも含まれますが、もっと深い意味(宗教上の意味)が込められています。「かげ」とは、神仏やご先祖さまの霊のことを意味しています。目には見えないものへの感謝の気持ちが込められる敬虔(けいけん)な祈りの心からきた言葉です。