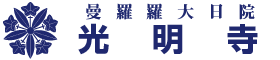見栄の仏壇と篤信の仏壇
2009年12月07日
お仏壇はとても立派なのですが、その前に座ると違和感のある家があります。よく見ると一部に問題があるのでそう感じるのです。例えばある家では線香を立てようとすると、香炉の中にマッチの燃えかすが何本も刺してありました。燃えかすの入れ物が無いため処置に困ってつい入れてしまうわけです。しかしこれは一番やってはいけないことです。「マッチ消しの一つくらいちゃんとそろえて下さいよ...マッチの燃えかすを香炉に入れるくらいならライターを置いときなさいよ...」と、思わず心の中でつぶやいてしまいます。その他にも、仏壇の荘厳はまことに立派なのですが、明らかに他宗派の様式と我が宗派の様式がごちゃまぜになっている仏壇や、読経の為に必要な仏具が揃っていない仏壇もあります。リンはそれなりの物があるのですが木魚がない家、そうかと思えば木魚があるのにリンが無い家があったりします。こういうのを「見栄の仏壇・置いてるだけの仏壇」と云います。このあたりをしっかり指導してゆくのが僧侶の責任ではありますが、これらの多くは仏壇を販売した際の仏具店にも原因があるのです。大物(仏壇本体)を売りたい一心で本体以外の付属品や仏具への配慮が欠落した結果がこのような事態を招いているのです。本来仏壇店(プロ)であれば宗派による荘厳のしきたりは当然心得ておくべきですが、これをまったく理解していない店が意外とあります。新しい仏壇が入った檀家の家に開眼供養に行くと、あろうことか他宗派の宗紋が入った提灯が下がっていたり、我が宗派では使用しない様式の打敷がかかっていたりします。あきれかえって怒る気にもなりませんが、悲しいかなこれが現実です。
こだわり住職は僧侶になって以来、本山で学んだ作法の読経を、出来るだけ忠実に再現することを心がけて来ました。我が宗派においては、本式に読経を行う場合は前記のリンと木魚以外にも伏鐘・音木・ケンツイなどと呼ぶ鳴り物も使用しますが、これらの仏具がすべて揃っている家はまずありません。もちろん一般家庭でそこまで揃える必要はないのですが、リンや木魚さえも無い場合があるので、法務の際には鳴り物一式や焼香用具一式などを常に持ち歩き、不足している仏具をおもむろに取り出して読経を行います。見ようによっては嫌みなくらい丁寧にやらせてもらっています。要は「揃えてもらえませんかねー」とハッキリと口に出来ない小心者の住職が、無言のアピールをしているわけです。
一方、篤信の(家の)仏壇の例もご紹介しておきます。お仏壇は新しいわけでも特別立派なわけでもありません。その家の先々代が入れられたものを今も大切に使われている家です。しかしいつ行っても仏壇の掃除は行き届いています。古いながらもリンは一般家庭用としては少々大きめで、正式なリン台にのせてあります。要するにお寺の本堂にある大型のリン(大型のものは本当はキンスと呼びます)と同じ様式です。木魚は使い込んでいるので表面が多少すり減っていますがまだまだ使えます。木魚をのせる丸座布団と木魚をたたく棒(バイと云います)は、消耗品なのできちんと更新してあります。同様にリンの座布団とリンをたたくリン棒も消耗品なので更新してあります。本体はいずれも古いものではありますが、その家の歴史が感じられて好感がもてます。法事の為に約束の時間に伺うと香炉にはすでに炭が入れてあり、着座すると直ちに焼香できるようになっています。こういうお宅の仏壇に向かうと私も人間ですから読経に集中でき、いっそう充実した法要が出来ることになってしまいます。(それではいけないのでしょうが・・・)さてみなさんのお宅はいかがでしょうか?