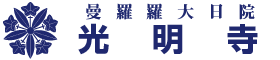慶宣が山寺にやってくる
2010年01月09日
お坊さんになる為に、とんでもない目にあったことを『1/4・おかげさまの話し』で書きましたが、その、とんでもない加行で同行人であった、中北慶宣君から年末に連絡がありました。2月の末に友人(たぶん)かなにかの結婚式に出席するので、はるばる長崎まで行くようになった。帰りに山口へ寄るから観光案内して欲しいという。要は「オッチャン、山口のおもしろいところへ連れてってよ、それから美味しいものもたのみます」と、いうことである。彼とは親子ほど年が離れていますが、約2年半に渡り定期的に本山で缶詰になっては、坊さん修行を一緒に続けた仲です。初めて本山で会ったときの彼はまだ18才でした。翌年の加行も一緒だったから、いわば同じ釜の飯を食った同期の桜(若い人にはなじまない言葉か?)です。実際には、加行の同期は同じ釜の飯というよりは、同じ石桶の冷水をかぶった仲と言うべきでありましょう。
その慶宣だが、よくよく考えてみるとうちの息子と同じタイプの人間である。今時の若者にしては実に素直で優しい性格である。人なつっこく他人から可愛がられるキャラである。ただ、少々おっとりし過ぎて「大丈夫かいな」と心配になることもあった。慶宣は名古屋の立派な寺の息子である。しかも、昨年早々だったかすでに父親の意向で住職に就任済みである。父親は私と同じで、母親の実家の寺を継ぐため在家から仏門に入った人であるという。その父親をひそかに尊敬し誇りに思っているのが、ひかえめな息子の話からも垣間見え、実にうらやましい師弟関係である。慶宣は良い師匠にめぐまれているのである。彼は仏教系の大学在学中に、我が宗派の僧侶と住職の資格を得るための修行を、私とまったく同じタイミングで続けた。そういうご縁で、私は京都市内にある彼のアパートに転がり込んで、ごろ寝したこともある。加行が終了し解散になった際には、私の運転する車で一路比叡山へ向かった。お念仏の教えを広められた法然上人は、元々は天台の僧侶である。いわば上人の原点でもある比叡山延暦寺の根本中堂へ、無事僧侶になれた記念として参拝することにしたのである。すでに公開時間は終わっており、駐車場の端にある拝観受付窓口はカーテンが閉じられて無人であった。それで、拝観料と少々の志を無理矢理窓口の隙間からねじ込み、人気のない参拝道を根本中堂に向かって二人で歩いた。根本中堂の門は閉じられているので、その扉の前に並んでお経を読み、丁寧に合掌礼拝して帰路についた。再び京都市内までもどると、慶宣のリクエストで気の利いた焼き肉店へ入り、娑婆に生還後の最初の食事として、少々贅沢なディナーを堪能したものである。
我々は毎年3月末頃に後に続く若い僧侶の加行見舞も兼ね、同行人会(同期会)を京都市内で行うので、まずは本山に集合する。後輩たちが行う水行を見守り「がんばれよ」と心の中で呟きながら合掌をした後は、先回りして御影堂(本山の本堂にあたる)の外陣に陣取り、彼らのおつとめに参加する。その後、御影堂に奉ってある西山上人像のおつとめを済ませた加行人たちは、次に控える経蔵のおつとめを行う為に、御影堂正面の回廊に姿を現す。我々は御影堂の階段下で向かい合わせに陣取って、一緒に読経を行うのである。毎年ここまでが、いわばお約束のコースである。「こいつら今年も来たか、よく続いてるのー」と、総監督である櫻井師の眼が少々笑っているのを見届けたら、私たちは本山を後にして同行人会の会場へ移動するのである。
今年も3月には慶宣と本山で再会するはずであるが、その前月に山口に来るという。さて、どうしたものか。山口の食い物といえば、この時期はなんといっても「ふぐ」である。やれやれ、大変な出費になりそうな気配である。しかし、我が山寺を見せてやったらさぞかし驚くことだろう。都市部のお寺とはあまりにも違う。おまけに極めつけのボロ寺である。「彼の社会勉強になるかもしれんなー」と、そんなことを考えながらその日を楽しみにしている。