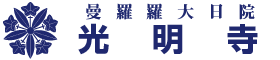秘密のあこちゃんの話し
2010年01月11日
慶宣のことを書いたのでその流れでもう一人、毎年3月末頃に本山で再会する僧名「妙照」こと、「あこちゃん」のことを書くことにします。あこちゃんも加行を一緒に耐えた同級生です。「死ぬかもしれんと思った...」と、随分情けないことを公言してはばからない私ですが、あこちゃんは、初めて会った時から(今でも)見るからに可愛らしい女性でした。そうなんです、女性でも同じことをやってるんです。だから、泣き言ばかりの私の加行体験談(1/4・おかげさまの話し)は少々軽すぎますね。まあそこらへんのことは今回は追求しないで、あこちゃんのことを話しましょう。彼女の家(寺)は和歌山県です。和歌山は我が西山浄土宗の勢力が強く末寺が非常に多い場所です。彼女は小学校の先生をしていました。最近の子供達はとても体格が良くて、小柄な彼女は子供達と一緒にいると区別がつきません。へたをすると子供とまちがえられそうです。とても愛くるしいというか、異常な若作りというか(失言かなー)まあ、そういう人です。女性シンガーの一青窈(ひとと よう)さんによく似てますね。その彼女がお坊さんになる道を選び縁あって私と同行人になっていたのです。
あこちゃんは子供達の先生をしていたこともあってか、話し方も独特の優しいしゃべり方で、相手を和やかな気持ちにさせてくれます。そんな彼女ですが、加行中には意外な一面を見せてくれました。すでに書いたとおり、加行中は一日三回水行を行い、いわば身体を清めた後におつとめをします。それが終わると食事です。その食事の用意は加行人の一部が当番で、配膳・給仕・後片付けを行います。この作業は限られた時間で行わねばなりません。本当はいけないのですが、本山の回廊を必死で走って準備に行きます。彼女とは当番がよく一緒でした。それで、のろまなオッサンはいつも足手まといになるわけです。これではへたをすると間に合いません。そんな時です。ほんわかした空気をまとい、おっとりした印象であった彼女が実にてきぱきと機敏でした。要領の悪い私に「あーだめだめ、吉村さんそんなことやってちゃだめ、この湯飲みをこうして並べて行ってお茶を入れて下さい。それが終わったら次はこれとこれをやって、その次は....」と、実に見事な采配ぶりです。ああ見えて芯はとてもしっかりした強い女性なんだと、感心したことしきりです。考えてみればこの加行に参加しているのですから、並大抵の女性ではありません。その彼女も今は立派にお寺を守っています。唯一の課題はお婿さんが来てくれることくらいかな?あこちゃん今度は婚活だね。私がもっと若くて女房子供がおらんかったらすぐ立候補するけどねー。えっ、あこにも選ぶ権利がある?やっぱりそう来たか。とにかく皆さん、あこをよろしくお願いします。
さて、見た目の印象とは違って実は芯の強い女性であった彼女ですが、加行のみならず住職の資格を頂くための修行(学問中心です)も、ほぼ同じタイミングで受けました。慶宣と同じように、定期的に本山で缶詰になり同じ時間を過ごした仲です。ただし加行をクリアして僧呂の資格を得た後、次にひかえる住職に就任できる資格を得る為の座学で必要な単位を取り、その卒業試験を受けるタイミングは、都合により私より一年後でした。この試験というのが思った以上に大きな壁です。いわば大学の卒論と同じ要領で論文提出となります。しかも後日提出した論文の内容に関して、試験官との質疑応答もあります。私の時は我が宗門の流祖「西山上人のお念仏の教えについて述べよ」という、大変な「お題」が課されました。いくら本山でいろいろ勉強させてもらったとはいえ、流祖の念仏の教えについて書くなんてとんでもないことです。いわば我が宗派の核心部分、おしえの神髄について述べなければならないわけです。大変難儀な課題です。正直なところ今でも「これが我が西山派の教えの神髄である」と、書き示すなんてようしまへん。結局、先達の著した書物や資料を引っ張り出して、あっちこっちをつまみ食いし、なんとかそれなりの形にするしかありませんでした。今思えばそうなるのも当然でした。こんな大きな課題に取り組むということは、否応なしに猛烈に勉強することになります。卒業論文はそれが最大の狙いであったのだと思います。そして、たとえ合格したとしても終わりではありません。勉強(修行)はその後も必要です。お坊さんの修行は一生続くものなのですから。
私が無事合格した翌年に、あこちゃんが書かねばならなかった論文のお題は「無常観について」でした。仏教の根本的な考え方「諸行無常」の「無常」について掘り下げて述べよです。あこちゃんは、このお題の論文を提出するにあたり、自分の書いた論文をメールで私に送ってきて添削して欲しいと連絡してきました。(意外にも私は彼女に頼りにされていたのです)私は前年に一応合格していますが、お題は違うしそんなことができるようなタマではありません。しかし彼女には随分助けてもらったのだからと、目を通すことを承諾しました。それでじっくり読ませて頂いたのですが、その論文の冒頭には意外なことが書かれていました。実は彼女には弟さんがいて、我が宗門のお坊さんでした。しかし数年前に不幸にも交通事故で亡くなられ、考え抜いた末に彼女が僧呂になる道を選んだ一連の経緯が書かれていたのです。(聞いていなかったので随分驚きました)その論文は、彼女の強烈な無常体験に裏付けられた深い思索が述べらた見事なものでした。まさに彼女にしか書くことが出来ない論文です。目を通した私はただただ感動しました。ここまで書けていて添削が必要でしょうか?「私がさわっていいものだろうか」と少々ためらいましたが、彼女の「どうしても」の言葉に押され、ほんのわずかな修正とこの論文に対して予想される質疑応答に関するアドバイスをしました。彼女のあの優しさの裏にこんな深い哀しみがあったとは。「人は悲しみが多いほど、人には優しくできるのだから」と、武田鉄也さんは歌いましたが、まったくその通りです。彼女の論文は今も私のパソコンに大切に保管してあります。