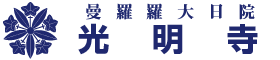音色の良し悪しってなに?
2009年12月26日
少年時代にギターの音色にさんざんこだわり、今思えば見事な「求不得苦」状態に陥っていた私の話『12/16 ギター少年の求不得苦』はすでに書きました。お坊さんになったこともあり、その愚かさを冷静に振り返ることが出来るようになったので書いてみたのですが(偉そうなこと言ってます)どっこい今でも相変わらず音に対する感性(格好いい表現だこと)は、まだまだ錆び付いてはいないと自惚れている全く懲りないオッサンです。お坊さんになって、その日々の中で音に関して一番気になってしょうがなかったのは、読経の際に叩く鐘(寺にある大きいのをキンスといい、家庭にある小さいものはリンといいます)の音色でした。私は音響学的な知識に詳しいわけではありませんが、学問的には音の三要素というものがあって、音の性質を決める要因の最も基本的なものは「大きさ」「高さ」「音色」だそうです。音の大小は空気の振動する幅の大きさで決まり、音程は振動する波(空気の振動)が1秒間に繰り返す回数(周波数・Hz)によって決まります。そして人が耳で聞いたときの音の印象というか、音の性質の違いを決定づける最も重要な要素が三番目の音色です。実際にはこれ以外にも音の性質を左右する要素はあるのですが、通常は影響が少ないのでとりあえずここでは無視します。
我々はよく音色がいいとか悪いとか口にしますが、いきなり「音色とはなんぞや?」と尋ねられて、科学的にきちんと説明できる人は限られると思います。音響学では音色を「周波数成分」と呼んでいます。音の高さ、すなわち音程は一番中心になる振動数の音(基音と呼ぶ)で決まりますが、この基音に「倍音」が加わることで音色が生まれるのだそうです。倍音は「基音の整数倍」の振動で、多数(理論的には無限個)現れるそうです。この倍音の含有率の違いで様々な音色が生まれるそうです。ですから音色の違いとは倍音の混ざり(発生)具合の違いであり、それはすなわち周波数成分の違いなのです。音程を決定しているメインの周波数以外の振動(倍音)は、極端な言い方をするとメインの振動から発生したオマケみたいな振動です。(あくまでも私の感覚的な表現ですが)しかし、これの混ざり(発生)具合で音色が決まるわけですから、オマケのようでありながら楽器の音色、すなわち楽器の値打ちを決定する重要な要素です。(それこそ、我々幼少期のグリコのおまけみたいです。おまけがとても重要だった)ところで、楽器や自然界の音には多数の倍音が含まれていますが、安物の電子楽器等はたいてい倍音が含まれていません。それで、誰が聞いてもいかにも人工的な音と感じるものです。これも人間の耳が倍音のあるなしをきちんと聞き分けているからでしょう。
さて、山寺の本堂にあるキンス(鐘)は、江戸時代天保12年に調達した骨董品です。ここまで古いと金属疲労が相当進行しているようで、叩いたときの振動時間(音が鳴ってる時間)は随分短くなっています。そして音色も冴えません。音の艶というか、響きかたの印象がよろしくないのです。キンスもいわば楽器みたいなものですから、光明寺のキンスの音色が良くないのは倍音の分布状態が良くないのでしょう。そもそも金属疲労の進行で、倍音の絶対的な発生量が激減しているようなのです。坊さんになってからは、このことが気になってしょうがなかった。困ったオッサンであります。繰り返しになりますが、楽器等の音の良し悪し、すなわち音色を左右する重要な要素は倍音であります。前述のとおり倍音とは通常は基音の整数倍なのですが、倍音が整数倍であるのは楽器や人の声などのケースで、これらの音は「楽音」と呼ばれます。ところがキンス等の金属等を叩いて音を出すケースでは事情が少々異なり、倍音は必ずしも整数倍とは限らないようです。それと、いいろいろ複雑な音(倍音ではない音)が同時に発生して独特な音色を作っているようなのです。そのあたりのことは、Google 等の検索サイトでヒットする「永観堂の梵鐘」というタイトルのPDFファイルが大変参考になります。梵鐘の音色の違いについて科学的な検証がされており、「実に奥が深いものなんだなー」と感じました。
永観堂は我が山寺が所属する西山浄土宗と同じ西山派の一派で、浄土宗西山禅林寺派の本山(禅林寺)の別名です。