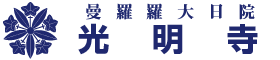総本山光明寺のおつとめについて
2010年01月01日
明けましておめでとうございます。さて、平成22年最初の記事をどうしたものかと迷ったのですが、本山のおつとめ(勤行)について書くことにします。わが山寺の本山である総本山光明寺は、山口から新幹線で新大阪まで行き、JRの在来線に乗り換えて京都方面へ向かうと、京都駅の4つ手前「長岡京駅」が最寄りとなります。(大阪市内からだと、阪急の長岡天神駅の方が近い)京都西山の静かな場所、長岡京市の粟生(あお)の里にあります。日が昇る前のまだ暗い時間帯から、本堂(本山は御影堂「みえどう」と呼びます)で毎朝おつとめが行われます。開始の合図の鐘が鳴ると巨大な木魚が打ち始められ「ナァーム、アーミ、ダァー、ブー、ナァーム、アーミ、ダァー、ブー、」とお念仏が称えられる中、我が宗派における頂点の僧侶、西山浄土宗の法主(我々宗門の僧は、法主を通常は御前さんと呼んでいます)のご入堂があり、おつとめが始まります。
まず「香偈」「三宝礼」「四奉請」が読誦されます。「香偈」は香を焚く時に称えるお経(偈文)です。「三宝礼」は仏教における三つの宝、仏・法・僧を礼拝するお経(偈文)です。仏は説明不要ですが、法は仏の教え(真理)のことで、僧は仏の教えを伝え導く人、つまり僧侶のことで広くは教団をさします。僧侶というと私もその端くれですが「この私も讃えなさいよ」といっている訳ではありません。(言われなくても解ってますよね)仏の教えを伝えてくれた、あるいは今伝え導いてくれる教団と、そこにおられる真の仏教者を礼拝しましょうという事です。「四奉請」は仏や菩薩を招へいするお経(偈文)です。このお経を称えることで仏や菩薩たちがこの場に降臨して下さり、道場として成立するのです。ですから、この三つのお経はおつとめを開始する前に行う三点セットの儀式です。メインディッシュの前に出される前菜みたいなものかも?(なんとも大雑把な解説です、関係者の皆様お許し下さい)通常はこの後に「開経偈」というお経(偈文)を読みます。今からお経を開きますよ(読みますよ)と宣言して、メインデッシュのお経(仏典)、たとえば「阿弥陀経」などを読誦し、その後に「礼賛偈」という独特のお経やその他のお経を読誦して行きます。しかし本山においては、そのメインディッシュが登場する前に「菩薩戒経」というお経も読みます。
日本の仏教は大乗仏教と呼ばれます。一人でも多くの人を救うため、覚りの世界行きの大きな乗り物を目指しているからです。また自分の修行(自行)だけでなく利他の行( 世のため人のための行)を重視します。この利他行の実践、すなわち自分だけでなく他の幸福を願う生き方を、仏教では菩薩が歩む道、「菩薩道」と呼んでいます。「戒律」という言葉があります。仏教徒をはじめ信仰を持つ者が守るべきルール、約束事、法律ですね。大乗仏教においては、菩薩の道を歩む者が受持すべき「戒」、すなわち「菩薩戒」が非常に重要なので、この菩薩戒のお経である「菩薩戒経」を本山では毎朝読誦しているのです。坊さんになりたての頃、私は「菩薩道」のことをが解るようになり「日本の仏教は菩薩道の実践だから、なるほどこれってとてもいいことだよなー、さすが本山だけのことはあるなー」と、ある意味感動に近い思いを抱いたものです。そして「菩薩戒経」に引き続き「天下泰平回向文」という極めつけの偈文が御前さん(法主)により称えられます。経文は次の通りです。
天下和順日月清明、風雨以時災厲不起、国豊民安兵戈無用、崇徳興仁務修礼譲
現代訳は「世界は平和で正しくあれ、歳月は清く朗らかであれ、天候は順調であれ、災害や疫病の起こらないようにあれ、国は豊であり人々は安らかであれ、兵器を用いることがないようにあれ、良い行いを崇(あが)め慈しみの心を持ち、真心をもって思いやりにつとめよ」です。御前さんは毎朝この偈文を称えておられます。ありがたいことです。坊さんになり少々勉強したおかげで、本山で毎日行われている「おつとめ」のありがたさを知りました。そして我が総本山だけではなく、多くの寺院でも多分同様のことが行われていることを推測できるようになりました。坊さんになっていなかったら気づく機会はたぶん無かったでしょう。
我が山寺では、元旦を迎えた本日深夜に修正会(新年を迎え一年の幸せを願う法要)のお勤めを行いました。その際には今年最初の「菩薩戒経」を読み、私なりの思いを込めて「天下泰平回向文」を称えさせて頂きました。